2025年のノーベル化学賞に輝いたのは、京都大学の北川進(きたがわ・すすむ)特別教授。
受賞理由は「多孔性材料(たこうせいざいりょう)」の開発。
──聞き慣れない言葉かもしれませんが、この研究は水素エネルギーや環境問題の未来を変える可能性を秘めています。
この記事では、「北川進さんとはどんな人物なのか?」「多孔性材料って何がすごいの?」をわかりやすく解説します。
北川進プロフィール
- 名前: 北川 進(きたがわ すすむ)
- 生年月日: 1951年7月4日(74歳)
- 出身地: 京都府京都市下京区
- 出身高校: 京都市立塔南高等学校(現・京都市立開建高校)
- 出身大学: 京都大学 工学部 石油化学科 卒業
- 学位: 博士(工学)
- 現在の職位: 京都大学 高等研究院 特別教授・理事・副学長
- 専門分野: 無機化学、配位化学、多孔性材料
- 主な受賞歴: 日本化学会賞(2009)、紫綬褒章(2011)、日本学士院賞(2016)、フランス化学会グランプリ(2019)、ノーベル化学賞(2025)
ノーベル化学賞の受賞理由:「多孔性材料」とは?
北川さんが開発したのは、分子レベルの小さな穴がたくさんあいた“多孔性材料”。
この材料は、「スポンジのように気体を吸い込むことができる特別な金属素材」です。
たとえば──
つまり、「空気中から欲しいガスだけをつかまえる魔法のフィルター」とも言えるもの。
この発見は、エネルギー問題・環境問題の解決に直結する技術として世界的に注目されています。
北川さんは1997年にこの仕組みを世界で初めて立証し、以降、世界中の研究者がこの「多孔性配位高分子(Metal-Organic Framework, MOF)」の研究に取り組むきっかけとなりました。
ノーベル化学賞とは?
ノーベル化学賞は、スウェーデンの王立科学アカデミーが毎年選出する、世界で最も権威ある化学の賞です。
化学の進歩に大きく貢献した人に贈られ、これまでに多くの日本人科学者も受賞しています。
過去の日本人ノーベル化学賞受賞者
| 受賞年 | 受賞者 | 業績 |
|---|---|---|
| 1981年 | 福井謙一 | 化学反応の理論(フロンティア軌道理論) |
| 2000年 | 白川英樹 | 導電性高分子の発見と開発 |
| 2001年 | 野依良治 | 不斉水素化反応に用いるキラル触媒の開発 |
| 2002年 | 田中耕一 | 温和な着脱イオン化法を開発 |
| 2008年 | 下村脩 | 緑色蛍光タンパク質(GFP)の発見 |
| 2010年 | 鈴木章・根岸英一 | クロスカップリング反応 |
| 2019年 | 吉野彰 | リチウムイオン電池の原型を開発 |
| 2025年 | 北川進 | 多孔性材料の開発 |
北川さんはこれらの偉大な化学者たちに続く、日本で8人目のノーベル化学賞受賞者です。
北川進さんのすごさをまとめると…
つまり、“空気の中にある見えないエネルギーをつかまえる力”を科学で作り出した人です。
まとめ
ノーベル化学賞を受賞した北川進さんは、「多孔性材料」という新しい化学の分野を切り拓いた世界的科学者です。
その研究は、未来のエネルギー利用や地球環境の保全に欠かせない技術へと発展しています。
長年にわたる地道な研究の積み重ねが、いま世界から最高の評価を受けました。
これからの化学の教科書に、きっと「北川進」という名前が刻まれることでしょう。
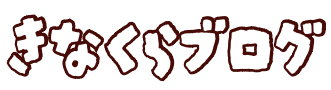
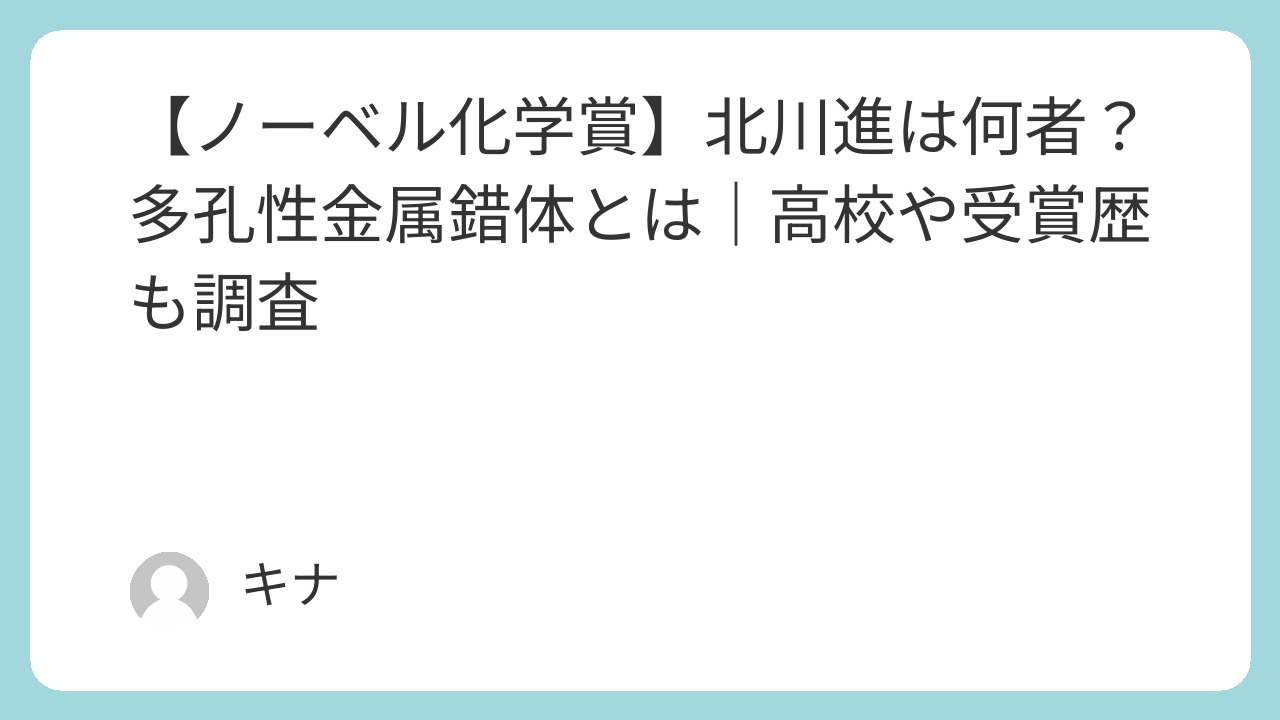
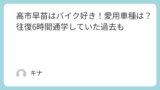
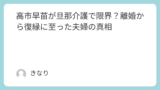
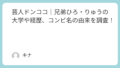

コメント