2025年の新語・流行語大賞ノミネートが発表されました。今年はSNSで話題を集めた「チャッピー」や、気候変化を象徴する「二季」、共感を呼んだ「長袖をください」など、多彩なワードが並びます。
本記事では、2025年を象徴する30の流行語の意味や誕生の背景をわかりやすくまとめました。それぞれの言葉が注目された理由を知ることで、今の時代をより深く読み解くことができます。
ネット・ドラマ・若者文化から生まれた流行語
Z世代を中心に流行した「ビジュイイじゃん」やNHK朝ドラ『あんぱん』から「ほいたらね」がノミネート。SNSで拡散されるなど世代を超えて広がりました。
長袖をください(SNSミーム化したフレーズ)
TBS系『水曜日のダウンタウン』の人気コーナー「名探偵津田」で、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏さんが発した一言が話題になりました。唐突でユーモラスな発言がSNSで拡散され、思わず真似したくなる言葉として注目を集めています。
エッホエッホ
「メンフクロウのヒナが草むらを懸命に走る姿」を撮影した写真が海外のSNSで話題になり、日本ではその姿に「エッホエッホ」という擬音を添えて紹介されました。写真を撮影・投稿したのは自然・野生動物専門の写真家ハニー・ヘーレ氏です。日本ではシンガーソングライターが「エッホエッホのうた」を公開したり、「エッホエッホ構文」としてSNS上で使われたりするなど、一躍ブームに。若者のあいだでは「急いで何かをしている様子」をあらわす言葉としても定着しました。
チョコミントよりもあ・な・た
人気メディアミックスシリーズ『ラブライブ!』のラジオ番組から誕生した期間限定ユニット「AiScReam(アイスクリーム)」のデビュー曲『愛ハートスクリ~ム!』がTikTokで話題になりました。
曲中のセリフ「チョコミントよりもあ・な・た」の部分が印象的で、多くのユーザーが動画で使用。アイドル文化とSNS文化の融合を象徴するヒットワードとなりました。
ビジュイイじゃん
男性ボーカルダンスユニット・M!LKの楽曲『イイじゃん』が話題になりました。TikTokで投稿された動画が人気を呼び、セリフ部分の「今日ビジュイイじゃん」というフレーズがSNSを中心に流行語となりました。ファンの間では日常会話でも使われるなど、若者文化に浸透しています。
チャッピー(意味・由来・話題になった理由)
アメリカの企業・オープンAIが開発した、AI(人工知能)を使って自然な会話を行えるサービス「ChatGPT」の愛称です。
親しみやすく呼びやすい名前としてSNSや動画配信などで広まり、「チャッピーに聞いてみた」などの表現が一般化しました。AIが日常生活の一部として浸透してきた象徴的なワードといえます。
7月5日
「7月5日午前4時18分に巨大津波が発生する」という根拠のない噂がSNSを通じて拡散し、香港や台湾の航空便が減便・欠航する事態にまで発展しました。
科学的根拠はまったくなく、気象庁や地震の専門家が否定するデマでしたが、恐怖をあおる情報の拡散力と人々の反応の速さが改めて浮き彫りになりました。噂の発端とされた書籍にも注目が集まりました。
ひょうろく
フリーのピン芸人・ひょうろくさんは、ドッキリ企画などで見せる「素なのか演技なのかわからない独特の表情」が注目されています。
その独特のキャラクターに魅力を感じるファンも多く、近年は俳優としても活躍の幅を広げています。NHK大河ドラマ『べらぼう』やフジテレビ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』など、話題作への出演も増えています。
ほいたらね
NHK連続テレビ小説『あんぱん』の舞台となった高知県の土佐弁で、「またね」という意味を持つ言葉です。劇中やナレーションでたびたび使われ、温かみのある響きが視聴者の心を和ませました。ほかにも「たっすいが」「たまるか」など、個性的な方言表現がドラマの世界観を豊かにしています。
社会・政治を映した流行語【ニュース系ワード】
物価高やトランプ関税など、2025年の社会情勢を象徴する言葉が登場しました。政治・経済・環境問題を反映したワードが注目を集めています。
トランプ関税
アメリカ大統領選挙で再選を果たしたトランプ大統領が、各国に対して実施している一方的な関税引き上げ政策を指します。
自国の利益を最優先する強硬な交渉姿勢が再び注目され、国際経済に大きな影響を与えています。各国の反発や貿易摩擦の懸念も高まり、世界がその動向を注視しています。
働いて働いて働いて働いて働いてまいります/女性首相
自民党総裁選で新総裁に選出された高市早苗氏が、決意表明の場で述べた言葉です。働き方改革が進み、ワークライフバランスが重視される時代において、「ワークライフバランスを捨てる」とも取れるこの発言には、賛否の声が上がりました。日本初の女性首相としての強い覚悟を示した言葉として注目を集めています。
卒業証書 19・2秒
静岡県伊東市の市長が、市議会から求められた卒業証書の提示を「19・2秒間だけチラ見せした」と報道され、世間の注目を集めました。学歴をめぐる問題としてメディアで連日取り上げられ、政治家の説明責任や透明性に関する議論が広がるきっかけとなりました。
戦後80年/昭和100年
2025年は「戦後80年」と「昭和100年」という二つの節目が重なる年でした。各メディアでは戦後の歩みを振り返る特集番組や記念イベントが多数企画され、書店でも関連書籍が多く並びました。
平和の尊さや歴史を次世代へつなぐ取り組みが、あらためて注目された一年となりました。
フリーランス保護法
2024年11月に施行された法律です。個人で業務を請け負うフリーランスが、不利な取引条件を押し付けられることを防ぐためのもので、報酬の支払いや契約内容の明確化などを企業側に義務づけています。働き方の多様化が進む中で、フリーランスにとって重要な法的保護の一歩となりました。
物価高
ここ数年、食料品や日用品をはじめ、さまざまなモノやサービスの値上がりが続いています。世界情勢の影響によるエネルギーや原材料価格の高騰も重なり、多くの人が生活の不安を感じています。この「物価高」は、2025年も引き続き社会的な関心が高いテーマとなっています。
古古古米
コメ価格の高騰が社会問題となった「令和の米騒動」をきっかけに注目された言葉です。政府が備蓄米を放出したことで、安価なコメを求める人々の行列が各地に出現しました。備蓄米には「古米」「古古米」「古古古米」「古古古古米」など保存年数に応じた区分があり、このユニークな呼称がSNSでも話題になりました。味や安全性、調理方法などへの関心も高まっています。
企業風土
2025年は、企業のジェンダー配慮や職場の安全性に関する意識の低さが相次いで問題になった年でした。組織としての危機管理や説明責任の欠如が露呈し、「声を上げづらい社内風土」が注目されました。立場の弱い人の人権を守るためにも、企業・業界全体での構造改革と意識改革の必要性が強く問われています。
教皇選挙
第266代ローマ教皇フランシスコの死去を受け、次の教皇を選ぶ「教皇選挙(コンクラーベ)」が行われました。投票の結果、アメリカ出身のロバート・プレボスト枢機卿が選出され、新教皇レオ14世が誕生しました。
同時期に日本で公開されたエドワード・ベルガー監督の映画『教皇選挙』も注目を集め、話題が重なったことでニュースとしても大きく取り上げられました。
緊急銃猟/クマ被害
改正鳥獣保護管理法の施行により、2025年9月1日から導入された制度です。
クマやイノシシなどが人の生活圏に出没した際、市町村長の判断で市街地での銃猟を可能とする仕組みです。近年、クマによる出没や人身被害が全国的に増加しており、地域住民の安全を迅速に確保するための対応策として注目されています。
オンカジ
「オンラインカジノ」の略称です。国内から海外のオンカジサイトを利用して金銭を賭ける行為は賭博罪にあたりますが、スポーツ選手や芸能人の利用が相次いで発覚しました。
海外では合法とされる場合も多く、罪の意識が薄れやすい点が問題視されています。気軽に始められる一方で依存性が高く、「仕組まれた依存症」として社会問題化。NHKスペシャルなどのドキュメンタリー番組でもその実態が取り上げられ、議論を呼びました。
オールドメディア
新聞やテレビといった歴史ある報道媒体を「オールドメディア」と呼び、不要・偏向的とみなす風潮が広がっています。一方で、短時間で理解できるTikTokや切り抜き動画などのSNSコンテンツが主流となり、情報の受け取り方にも変化が見られます。
オールドメディア批判が盛り上がる一方で、ネット上の情報に流されず、正確に見極める力の重要性が再認識されています。
二季(気候変化を表す新語として話題)
酷暑が続いた日本列島では、地球温暖化の影響により「春夏秋冬」という四季が失われつつあり、「夏」と「冬」の二季化が進んでいるといわれています。季節の移ろいを感じにくくなったという声も多く、気候変動を象徴する言葉として話題になりました。
生活・文化を反映した流行語【ライフスタイル・社会変化】
「おてつたび」や「薬膳」など、暮らし方の多様化を表す言葉が並びました。健康志向や新しい働き方を反映するワードが増えています。
おてつたび
「お手伝い(短期アルバイト)」と「旅」をかけあわせた造語です。人手不足に悩む地方の宿泊施設や農家などと、「旅先で働きたい人」をつなぐマッチングサービスとして注目を集めています。観光と地域貢献を両立できる新しい旅のスタイルとして、若者を中心に人気が広がっています。
平成女児
1990年代後半から2000年代初頭に小学生だった女子(現在20~30代)が、当時のキッズ文化を懐かしむ流行を指します。パステルカラーやリボン、ハートなどのモチーフが再び注目され、「平成レトロ」の派生として広がっています。SNSを中心に、当時のグッズやファッションを再現する投稿も増えています。
ぬい活
「ぬい活」とは、ぬいぐるみと一緒に行動する活動のことを指します。お気に入りの「ぬい(ぬいぐるみ)」をバッグに付けたり、外出先や旅先で写真を撮ったり(ぬい撮り)、ぬいの服を手作りしたりするなど、その楽しみ方はさまざまです。推し活文化とぬい撮り文化の融合によって、ここ数年で定着したライフスタイルです。
ラブブ(アートトイ人気から派生)
香港出身のデザイナー、カシン・ローン氏が生み出したウサギ耳とギザギザの歯をもつキャラクター「ラブブ」が話題になりました。K-POPアイドル・BLACKPINKのリサさんが紹介したことをきっかけに、世界中でブレイク。日本でも高校生を中心に、スクールバッグにぬいぐるみやキーホルダーを“じゃらじゃら”と付ける文化が再び広がっています。
リカバリーウェア
リカバリーウェアとは、繊維に練り込まれた鉱物が遠赤外線を放出し、血行改善や疲労回復をサポートすることを目的とした衣服です。体から放射される赤外線を吸収・再放射することで体表を保温し、血流や血液中の酸素濃度を高める効果が期待されています。効率的に睡眠や休息をとりたい現代人のニーズに合ったアイテムとして人気が高まっています。
ミャクミャク
大阪・関西万博の公式キャラクターです。誕生当初は「不気味」「怖い」などと不人気でしたが、その独特なビジュアルが次第に話題を呼び、一転して大ブレイクしました。ぬいぐるみやキーホルダーなど、さまざまな関連グッズが登場し、全国的な人気キャラクターへと成長しました。
国宝(観た)
原作・吉田修一氏、監督・李相日(リ・サンイル)氏による映画『国宝』が幅広い世代で話題となりました。上映時間は約3時間と長編ながら、「国宝観た?」というフレーズがSNS上で飛び交うほどの人気に。
任侠の世界に生まれ、歌舞伎役者として生きる喜久雄と、名門の家に生まれた俊介という2人の生き様を描いた、伝統×任侠×青春の物語です。原作を読んでから観るか、観てから読むか――という楽しみ方も話題になりました。
薬膳
薬膳は、季節ごとの旬の食材に薬膳効果のある食材を組み合わせ、からだをととのえる身近な料理として注目されています。
NHKドラマ『しあわせは食べて寝て待て』の影響もあり、自分でも試してみたいという人が増えました。近年はレシピ本も多数出版され、健康志向の高まりとともに、薬膳ブームが続いています。
麻辣湯
中国・四川省発祥のスープ料理「麻辣湯」は、花椒のしびれる辛さと唐辛子の辛さをあわせもつのが特徴です。具材や辛さを自分好みにカスタマイズできる点が人気で、2024年後半から専門店の数が増えています。辛党の間でブームとなり、SNSでも「自分だけの麻辣湯」を紹介する投稿が話題になりました。
まとめ|2025年の流行語が映す時代のキーワード
2025年の流行語は、社会や文化、そして人々の心の動きを映し出す鏡のような存在です。SNS発の言葉や社会問題、食トレンドなどが混在し、「多様化する価値観」と「時代のリアル」が浮き彫りになりました。どの言葉が大賞を受賞するのか、今後の発表にも注目です。本記事を通して、今年の流行語から見える“2025年の今”を感じ取ってみてください。
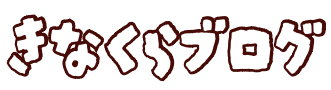
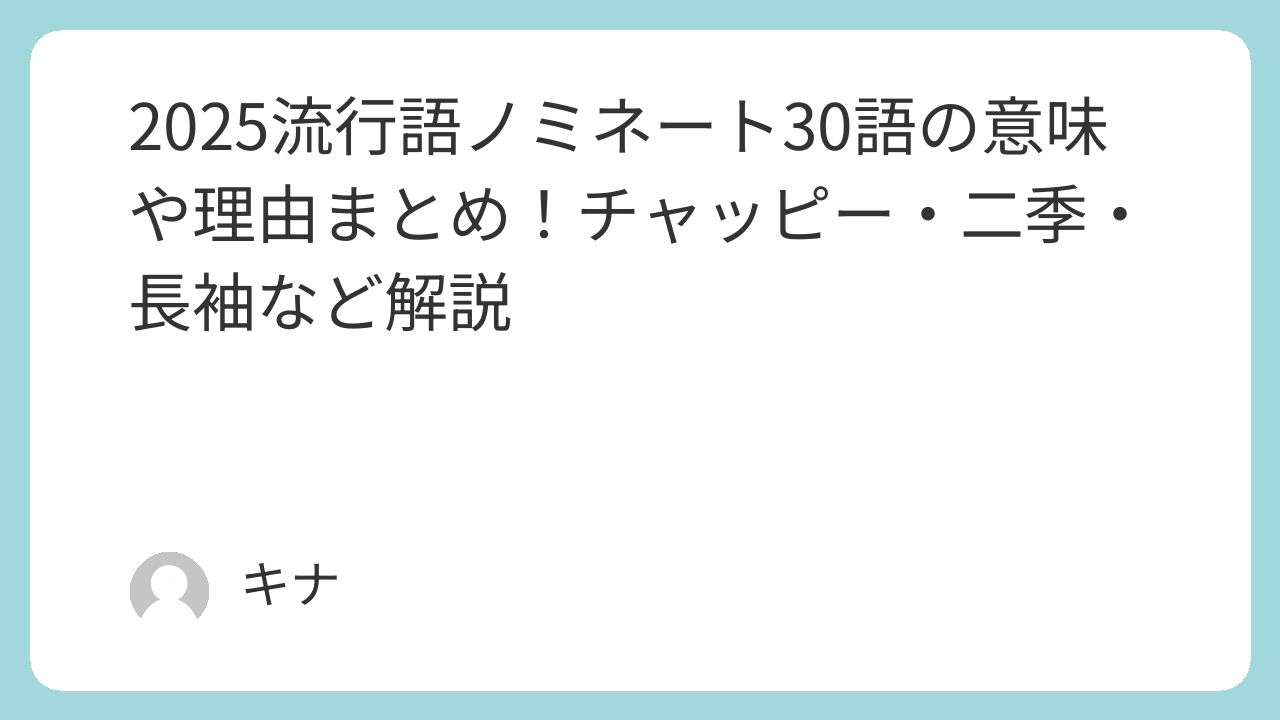
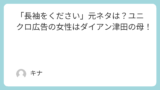
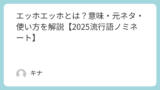
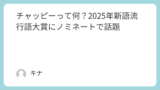
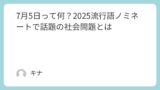
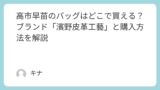
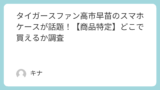
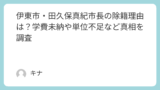
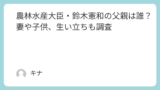
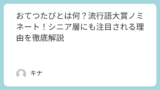


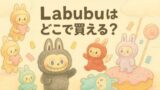
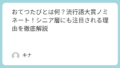
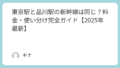
コメント