元東京都知事として活躍した舛添要一氏。2016年の突然の辞任から8年以上が経過した現在、彼はどのような活動をしているのでしょうか。
本記事では、舛添氏の現在の仕事内容と、都知事を辞めた理由について詳しく解説します。
舛添要一氏のプロフィール
舛添要一氏は1948年11月29日、福岡県北九州市生まれの国際政治学者です。東京大学法学部政治学科を卒業後、パリ、ジュネーブ、ミュンヘンでヨーロッパ外交史を研究し、東京大学教養学部で政治学助教授を務めました。
2001年に参議院議員に初当選し、2007年から2009年まで安倍内閣、福田内閣、麻生内閣で厚生労働大臣を歴任しました。
2014年2月には東京都知事に就任しましたが、2016年6月21日付で辞職しています。
舛添氏が都知事を辞めた理由
政治資金の公私混同問題
舛添氏が都知事を辞任した最大の理由は、政治資金をめぐる公私混同疑惑でした。
2016年5月11日発売の『週刊文春』で、千葉県のホテルでの家族旅行費用を政治資金として計上していた問題が報じられ、これをきっかけに様々な疑惑が次々と明らかになりました。
具体的な問題点
主な問題として以下の点が指摘されました。
- 公用車を使用して東京都庁や公舎と湯河原町の別荘を1年間で48回往復していたこと
- 海外出張費用が東京都の条例が定める宿泊費の上限を超えていたこと
- 正月の家族旅行の費用を会議費用として政治資金から支出していたこと
- 美術品の購入など、政治活動とは関係のない支出が多数あったこと
辞任に至る経緯
2016年6月1日から始まった都議会で、議員らがこの問題を追求しましたが、舛添氏は十分な説明を行わなかったため、辞任を求める世論が急速に高まりました。
当初は知事の座にとどまろうとしていた舛添氏でしたが、与党の自民党と公明党を含む都議会の全会派が不信任決議案を提出し、可決が確実になったため、2016年6月15日に辞職願を提出しました。参議院選挙(6月22日公示)への影響を懸念した与党も、不信任案提出に踏み切ったとされています。
舛添要一氏の現在の仕事
国際政治学者としての活動
都知事辞職後、舛添氏は国際政治学者としての活動を再開しています。
株式会社舛添政治経済研究所の所長として、国際情勢や政治について分析・発信を続けています。
執筆活動
辞職後も精力的に執筆活動を行っており、以下のような著書を発表しています。
- 『都知事失格』(2017年、小学館)
- 『ヒトラーの正体』(2019年、小学館新書)
- 『ムッソリーニの正体』(2021年、小学館新書)
- 『スターリンの正体』(2022年、小学館新書)
- 『プーチンの復讐と第三次世界大戦序曲』(インターナショナル新書)
- 『現代史を知れば世界がわかる』(2024年、SBクリエイティブ)
メディア出演とコメンテーター
テレビのコメンテーターとして国際情勢や政治について解説を行っており、JBpressなどのウェブメディアにも定期的に寄稿しています。
2025年10月には、高市政権に関する記事を執筆するなど、現在の日本政治についても積極的に発言を続けています。
YouTubeでの情報発信
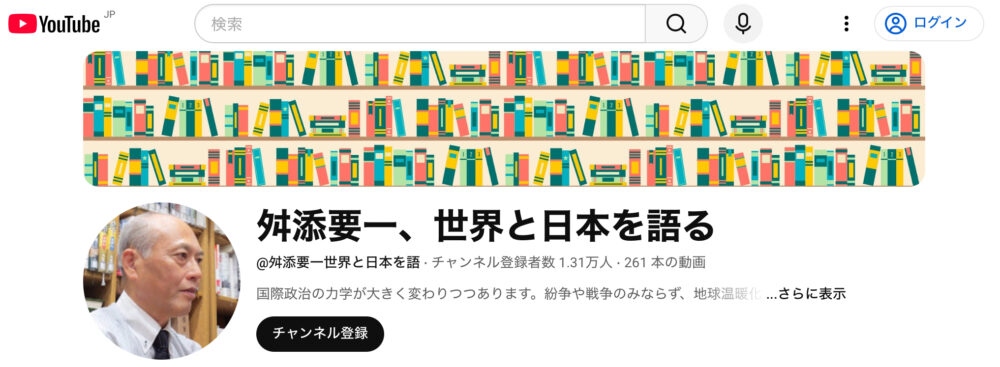
『舛添要一、世界と日本を語る』というYouTubeチャンネルを運営しており、最新の時事問題について自身の見解を発信しています。
チャンネルでは、国際政治の動向や日本の政治状況について詳しく解説を行っています。
講演活動
2024年9月には、世田谷区立保健医療福祉総合プラザで「小説で世界を歩く」と題した講演会を開催するなど、講演活動も継続しています。
この講演では『風と共に去りぬ』を題材に、歴史背景から現代のアメリカ政治まで幅広く解説しました。
国際交流活動
2024年3月には、北京で開催された第3回「民主:全人類共同価値」国際フォーラムに参加し、気候変動や感染症などの地球的課題について「人類運命共同体」の視点から取り組む必要性を訴えるなど、国際的な場でも活動を続けています。
まとめ
舛添要一氏は、2016年の政治資金問題による都知事辞任から8年以上が経過した現在も、国際政治学者として活発に活動を続けています。執筆、講演、メディア出演、YouTube配信など、多岐にわたる形で国際情勢や政治についての情報発信を行っており、その専門知識を活かした活動を展開しています。
都知事時代の問題は大きな批判を浴びましたが、現在は学者としての本分に立ち返り、国際政治の分野で専門性を発揮する日々を送っていると言えるでしょう。今後も、その豊富な知識と経験を活かした発信活動が期待されます。
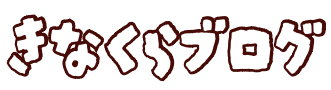
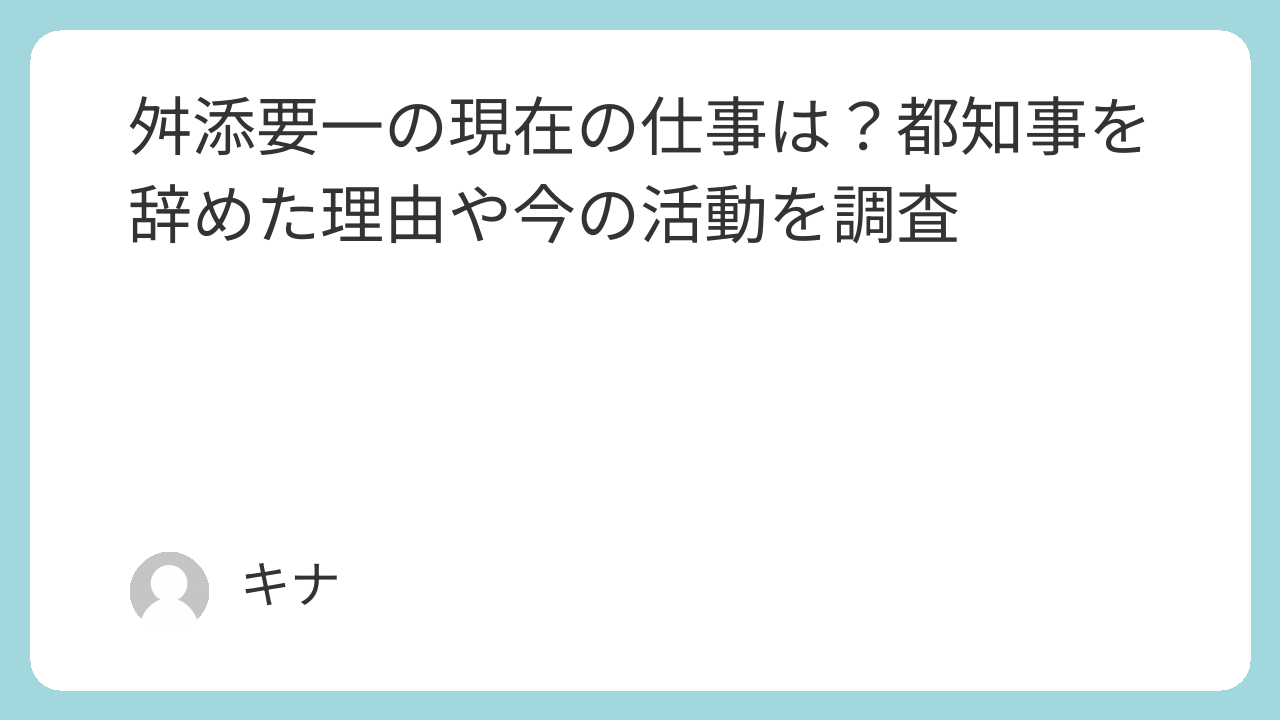
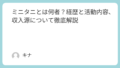
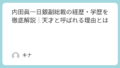
コメント