プラッシーは、1958年に武田食品工業から発売されたみかん果汁入り飲料で、ビタミンCを添加したことから「プラスC」という意味を込めて「プラッシー」と名付けられました。昭和30年代から50年代にかけて、特に米屋を中心に販売され、多くの家庭で親しまれた懐かしの清涼飲料水です。

オレンジ色の瓶に入った姿は、当時の子どもたちにとって憧れの飲み物でした。テレビコマーシャルでは「お届けします プラッシー」というコマーシャルソングが使われ、1カートンで1個グラスがついてくるという特典も人気の理由でした。
なぜお米屋さんで販売されていたのか?
多くの人が疑問に思う「なぜプラッシーは米屋で売られていたのか」という問いには、明確な理由があります。
武田薬品の販売ルート戦略
母体が製薬会社である武田は小売店への清涼飲料水の販売ルートを持たなかったため、流通経路を米穀店に絞りました。
実は武田薬品は、プラッシーよりも前に「ポリライス」というビタミン強化米を販売しており、すでに米穀店への販売ルートを確立していたのです。
栄養補完という発想
主食の米に不足な栄養素を補ってもらおうとビタミンCの入った飲料プラッシーを販売していました。白米には様々な栄養素が含まれていますが、ビタミンCはまったく含まれていません。
そのため、米と一緒にビタミンCを補給できる飲料を販売するという、製薬会社ならではの健康志向の発想があったのです。
宅配システムとの相性
昭和の時代、米の小売りが主に米穀店の配達によっていた時代は、その配達のついでに重い瓶入り飲料をまとめて自宅まで届けてくれるという点が売りでした。当時は自家用車が普及していなかったため、重い瓶入り飲料を家まで運んでもらえるサービスは大変重宝されました。
米を食べない家庭はほとんどありませんでしたが、お酒を飲まない家庭は存在します。つまり、米屋は最も汎用性の高い配達インフラだったのです。
プラッシーの誕生背景と時代性
戦後の栄養不足の時代、日本人の健康状態を改善することは重要な課題でした。みかん果汁入飲料の中にビタミンCをプラスしたことから、「プラスC」、「プラッシー」と製品名がつけられました。
武田薬品工業は製薬会社としての知見を活かし、栄養強化という観点から食品事業に参入しました。米屋での販売という独自の流通戦略により、スーパーマーケットが今ほど普及していなかった時代でも、全国の家庭にプラッシーを届けることができたのです。
プラッシーの種類とバリエーション
種類は瓶・缶・ペットボトル含めて、オレンジ、つぶつぶプラッシー、グレープ、サワーアップル、トマト、レモン、プラッシー50など様々なバリエーションが展開されました。初期は瓶入りが主流でしたが、時代とともに缶やペットボトルも登場しました。
プラッシーの終売と復活
競合商品の増加や瓶入り飲料の衰退、自家用車の普及による米の宅配の減少などにより、1980年代に生産中止となりました。しかし、復活を望む声や健康志向の高まりから、1998年にリニューアル新発売されました。今度は米穀店だけでなく、スーパーマーケットやコンビニエンスストアでも販売されるようになりました。
「プラッシーオレンジ」と「PLUSSY1000 おいしい鉄分」は2021年3月に、「プラッシーアップル100」は9月にそれぞれ製造を終了しました。清涼飲料としては終売となりましたが、「プラッシー」ブランドはハウスギャバンに移管され、介護向け水分補給ゼリーとして製造・販売されています。
プラッシーにまつわる都市伝説
清涼飲料としては米穀店で販売されていたため、「米のとぎ汁が使われている」という都市伝説がありました。また、添加されているみかんパルプが紙パルプであると誤解されることもありました。もちろんこれらはすべて誤った情報です。
まとめ:プラッシーが米屋で売られていた理由
プラッシーが米屋で販売されていた理由をまとめると、以下の3点になります。
1. 販売ルートの活用: 武田薬品が既に持っていた米穀店への販売網を活用
2. 栄養補完の発想: 米に不足するビタミンCを補うという健康志向のコンセプト
3. 配達システム: 米の宅配と一緒に重い瓶入り飲料を届けられる利便性
プラッシーは、時代背景と企業戦略が見事にマッチした昭和の名品と言えるでしょう。現在は清涼飲料としては終売となりましたが、水分補給ゼリーとして形を変えながら、そのブランドは今も受け継がれています。
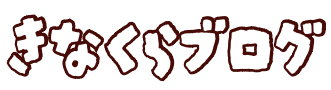
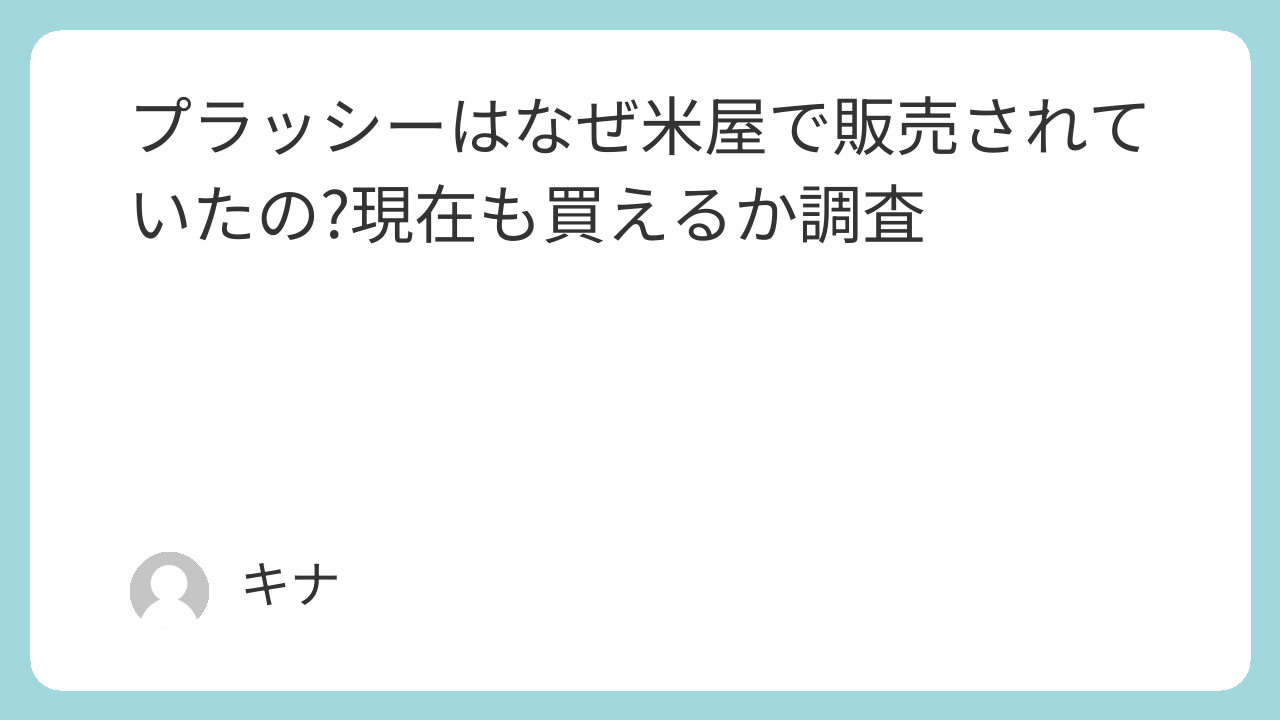
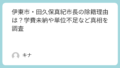
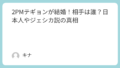
コメント